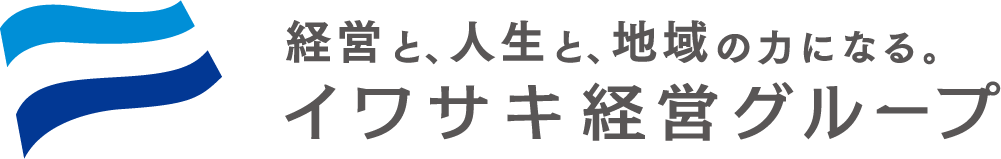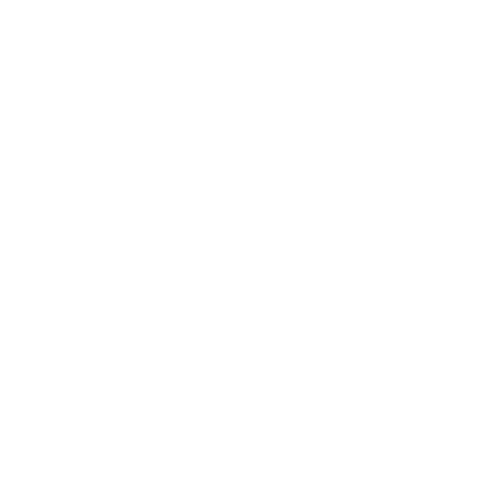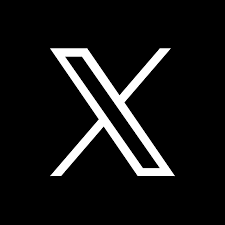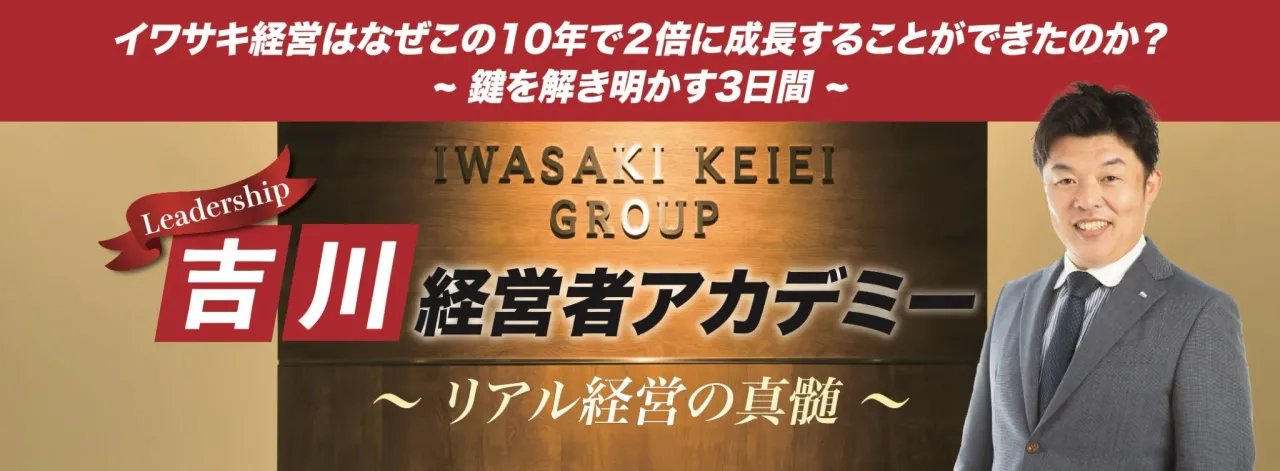イワサキ経営スタッフリレーブログ
2025.11.18
分かりにくい優しさ
私法と公法という言葉があります。私法は、個人間の関係を規律する法律で、代表的なものは民法です。一方で、公法は国や地方公共団体と個人との関係における法律で、刑法・行政法などが該当します。租税に関する法律は行政法の仲間なので、私が普段仕事で関わるのは公法ということになります。
所得税法や法人税法の条文は、悪文ともいえるほど難解な表現がされているものがあります。実務家の我々も、読むのに苦労するほどです。でも、表現が難しくなることには理由があります。
私法の争いは、当事者が納得する落としどころを見つけることが重要です。和解という解決策もありますね。これは私的自治の原則と呼ばれ、私法上の条文関係は、一定の制限はあれど、基本的には個人の自由な意思に基づいて自由に形成されるべきである、という考えに基づいています。
では、公法(租税法)はどうでしょうか。税金を誰に、どのような計算で課すかは必ず法律で決められています。裏を返せば、同じ条件に合致する人たちは同じように税金を課さなければならない、ということになります。理論上、和解はありません。かえって不公平さを生んでしまいます。
日本は申告納税制度を採用しているので、法律・条文(ルールブック)を読んで、自分がどの条件に合致しているのか判断し、税額を計算・納税することが求められています。だから、ルールブックを読んだ人たちができるだけ同じ結論にたどり着くように細かく書かなきゃ、となり、非常に読みにくいものになっているのです。本末転倒のような気もしますが、必要性は理解できるように思います。
過去の裁判事例を読むと、納税者にとって冷たい判決のように見えるものもあります。でもその冷たさは、条文そのものや、それが規定された趣旨に立ち返って、公平・公正な課税を目指すための判断の結果なのではないか。優しさの一つの種類なのではないかと思う時もあります。
なんかかっこいいですね。
実務的には、条文を読むだけでは判断できないことも山のようにあります。我々は、過去の裁判でどのように判断されたのかを知ることによって、条文を深く理解する必要があります。日々勉強です。
イワサキ経営グループ監査部一課 宇田川麻美