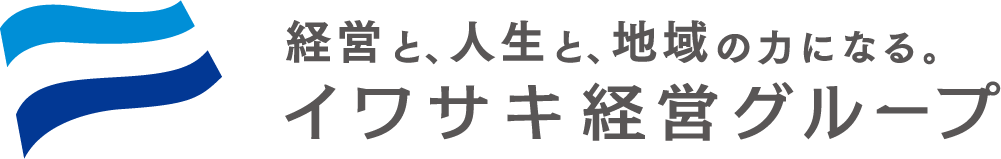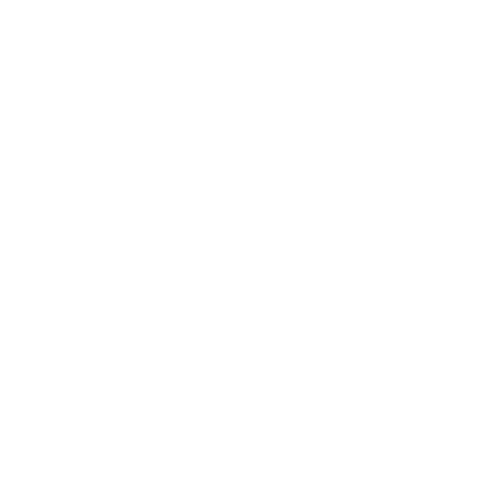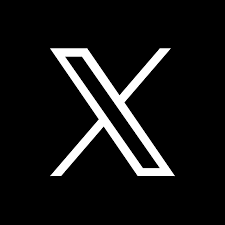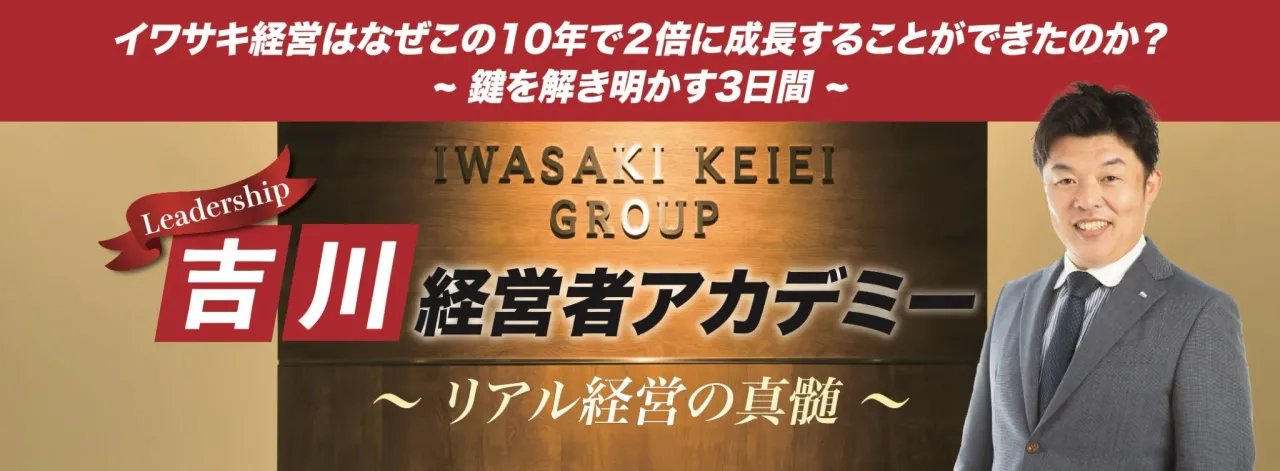イワサキ経営スタッフリレーブログ
2025年01月
2025.01.15
「綿の帝国」から見る資本主義の考察
自分がたまたま見かけたX(旧Twitter)のポストで、アフリカの中でも貧しいとされる地域に服を寄付する行為がいかにその国の経済を壊すかという記事がありました。
安価どころか無償で衣服が供給されてしまう状況において、衣服を生産して売るという経済活動は存在を否定されてしまいます。
そのポストのコメント欄に「綿の帝国」という本が面白いから読んでみてほしいという旨の書き込みがあり、値段を調べたら少々高かったものの興味を惹かれて買いました。
この本は単なる綿花産業の歴史書ではなく、産業革命から始まるグローバル経済の成長や、資本主義の基盤がどのように形成されていったのかを掘り下げて書かれています。
欧米諸国の産業革命による綿業の発展史というよりも、欧米による綿花栽培地域と綿織物産地、そして労働者に対する暴力と収奪の歴史に重きが置かれていて、これを読むことによってなぜ18世紀後半まで綿織物の技術力でイギリスを上回っていたインドが、逆にイギリス産綿織物の市場にされたのかも理解することができます。
収奪、という言葉を別の場所でも聞くことができます。
スウェーデンの王立科学アカデミーが2024年のノーベル経済学賞の受賞者を発表しました。
マサチューセッツ工科大学のダロン・アセモグル教授ら3人の授賞理由は、「『制度がどのように形成され、国家の繁栄に影響を与えるかの研究』を行い、これが法の支配が貧弱な社会や国民を搾取するような制度は成長やより良い変化をもたらさない理由を理解することに役立っている」からとのことです。
その受賞に際して、アセモグル教授は「植民地の場所によって、ヨーロッパ各国はそれぞれ異なる政策をとっていたが、収奪的な社会制度となっていた地域や国が大変貧しくなっていることを発見した。(中略)経済学者は、いわゆる経済と呼ばれる対象だけに分析を限定しがちだが、もっと広く政治体制や社会体制に注目した」と述べています。
資本主義の正解は今後の歴史が証明していくとして、不正解の一つは今までの歴史から収奪的な社会体制が挙げられる、ということを学びました。
イワサキ経営グループ 相続資産税課 堀場竜介
2025.01.06
生命保険の掛け方にご注意を
皆様は生命保険を掛けていらっしゃいますか?
ご自身に万が一が起こった際に葬儀費用や諸々の費用の支払いとして使用するための死亡保険金。掛け方一つで思いもよらない税金が掛かることがあります。
保険契約については保険料の支払い者・契約者・被保険者・受取人とあり、その中で課税に影響するのは保険料の支払い者です。通常であれば保険料の支払い者=契約者となることが多いのですが、まれに子供の保険を親が支払うことや孫の保険を祖父母が支払うことがあるケースが見受けられます。
上記のケースは①保険料支払い者Aさん・保険の契約者Bさん・被保険者Bさん・保険金の受取人Aさんというようなケースや②保険料支払い者Aさん・保険の契約者Bさん・被保険者Bさん・保険金の受取人Cさんというようなケースもあります。①のような契約の場合、Bさんに万が一があった場合にAさんがお金を受け取ることが出来るため、Aさんの所得扱いとなり一時所得が課税されます。Bさんが保険料を支払っている状態であればBさんに万が一が起こった際にAさんに死亡保険金が入るため相続税としての処理になり、相続税では死亡保険金の非課税枠(法定相続人の人数×500万円)までは非課税で受け取れますので、税金がかかる可能性は低くなります。
②のような契約の場合、Bさんに万が一が起こった際にCさんに死亡保険金が入るという契約になっておりますが、実際の保険料の支払い者がAさんのため、Aさん→Cさんへの贈与という扱いになります。死亡保険金などは金額が大きくなる場合がありますので、贈与税が課されるときは多額の納税になる可能性がございます。
そして上記①・②両方に言えることですがBさんがご健在の間にAさんに万が一があった際には、Aさんの相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんが亡くなった時点での解約返戻金の金額が相続財産となります。相続税対策として活用される保険ですが契約の内容によっては全く対策になっていない保険なども過去に何度か確認しています。子供の保険を親が払うという契約になっていたため解約返戻金が相続財産となり相続税申告が必要となってしまった方もいます。生命保険は自身で払うようにしておきましょう。
イワサキ経営グループ 相続資産税二課 長田浩明
- 1 / 1